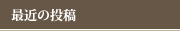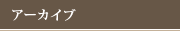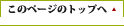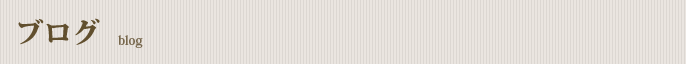
「お寺」と聞くと、あまり良いイメージがないようです。
「付き合いが煩わしい」「寄付が大変」「行事の参加がイヤ」などを、よく耳にします。
確かに、最近のご近所付き合いなどの希薄さから考えると、不向きな方もいるでしょう。
では、自分で体験した方が、どれだけいるでしょうか?
噂だけを信じて、所謂「食わず嫌い」はありませんか?
少なくとも、昭和40年頃から登場した「民営霊園」を求める以前は、殆どが寺墓地がでした。
お寺の中には、「寺檀関係」に胡坐をかいて、横暴な住職が居るのも、事実です。
ただ真面目に、お勤めされている住職が大半なのも事実です。
また「うちの寺の住職さんは、素晴らしい」などとは、あまり聞きません。
つまり、悪い噂だけが広まっているとも言えます。
ここで勘違いし易いのは、寺は住職個人の物ではない・・と言うことです。
施設が檀信徒のものなのですから、修復や改築の費用を、負担するのは当然とも言えます。
頻繁に寺に足を運ばないのは、個々の勝手ですから、使ってもいない施設の費用は支払いたくない・・では
道理が通りません。
本来、寄付とは個々の資力に応じて、応分の負担が原則ですが、檀信徒の数によっては、多額になる可能性はあ
ります。
また、葬儀や法事などを、同じ住職に依頼出来る「安心感」は、貴重です。
しかし、試しに求める訳にもいきません。
一つの目安は、そのお寺で、法事や彼岸以外の行事をどれだけ行っているか・・
例えば、「座禅教室」や「写経」などの、啓蒙活動です。
これにより、本来の「布教」への熱心さが計れます。
また、近隣の評判も大切です。
住まいの近くに、同じ宗派のお寺の有無も、必要条件です。
近所に良いお寺があれば、霊園での「宗教色」の問題も起こりませんから、一番安心とも言えます。
今一度、歴史」の重みや、伝統の良さを、再認識する必要がある時代かも知れません。
宗教色とは、宗教的な制約を指します。
ですから、入檀が前提の寺院墓地は、この章では除外します。
霊園などの広告では、「宗教宗派不問」や「宗教自由」などを前面に掲げています。
その時点では、事実でしょう。
問題は、完売後に起こる可能性があることです。
霊園などの名称で近年は「メモリアルパーク」や「メモリアルガーデン」或いは
「メモリアルフォレスト」などカタカナの名称が増えています。
あくまでも、共同墓地の固有名詞で、宗教不問の代名詞ではありません。
通常、霊園では完売後の収入は、年間管理料のみです。
管理料は、個々の墓地の維持費ではなく、通路や植栽の手入れ、管理業務に使用する光熱費や
管理事務所の人件費などの維持費に充てます。
これらの費用を全て「管理料」で賄えなければ、霊園の維持が出来ないと言うことになります。
管理料以外では、墓参用の花・線香の販売などの売上や、会食の席料なども含めた総収入で賄えるかどう
か・・です。
例えば、総区画数が500基で、1区画の平均の年間管理料が5,000円の場合、250万円が霊園の収入です。
光熱費や、人件費だけでも、到底賄えません。
前にも述べた様に、霊園の申請は「宗教法人」で行いますので、この宗教法人(寺院が多い)が、人件費などが
赤字であれば、園内での読経や法要を受けること(強制を含め)で、賄うことを考えます。
管理料の5,000円を20,000円にすれば、賄えますが利用者からの理解を得られないでしょう。
ここで「宗教色」が発生します。
利用者全員が、宗派やお経が違っても、苦情が出なければ問題ありません。
仏教徒ならまだしも、キリスト教や神道は「宗教」が違いますし、新興宗教と呼ばれる信者さんは、「在来仏教」
の否定から始まっているケースが多いので、受け入れは困難です。
地方自治体が運営する「公営霊園」でない限り、この問題は、どこの「民営霊園」でも起こる可能性はあります。
全ての自治体に「公営霊園」がない以上、「民営霊園」を求める選択肢しかない方もいます。
これを防ぐには、「管理料」だけで運営出来る(或いは出来そうな)「民営霊園」を求めるしかありません。
年間管理料が5,000円だとすれば、最低2,000基の規模が必要です。
毎年、1,000万円以上の収入が、コンスタントにあれば運営は、出来ると思います。
勿論、それでも未来永劫に亘って「宗教色」が出ないとは限りませんが、かなりの安心材料です。
墓地を選ぶ時点で、完売後まで考慮して検討する方は、少ないとは思いますが、お墓は買い替えが
出来ない以上、30年・50年単位で考えなければなりません。
お子さんやお孫さんの代まで、気持良く墓参が出来る「お墓選び」を心掛けたいものです。
距離や設備などの表面に出ていること以上に「宗教色」は、重要事項です。
見学の際に、「予定される総区画数」や「近隣の拡張の余地の有無」などを、チェックするのも肝心です。
求めるのはすぐですが、墓参は末代までですから・・
設備は、墓地の形態により異なります。
寺院墓地では、「本堂」「庫裡」「客殿」「駐車場」などが主要施設です。
「庫裡」とは、寺の代表役員である住職の住まいのことです。
「客殿」とは、檀家さんの会食や休憩の為の施設です。
老朽化すると、檀家さんの「寄付」で立て直すことが一般的ですが、稀に住職の方針により異なります。
霊園などでは、これに代わり「休憩所」や「礼拝堂」などを設置することがあります。
休憩所の一部に「会食場所」を設けている霊園もあります。
これらの施設の設置の為に、墓地使用料や管理料に反映されることもあります。
利用料金がその都度発生することが多いようです。
将来の建て替え時に、年間管理料だけで賄えるのかも、気になるところです。
また、会食は仕出しが多く、業者が指定されることがあります。
その場合は、好みの味や価格を選べない・・ということです。
つまり、施設があっても、全て自由に使用出来るとは限りません。
法要が土日の昼前後に集中するので、先着順が基本です。
近隣に、会食場所があれば、そちらでカバーすることも可能です。
必要なのは、どこまでの施設を重視するか、制約などの条件の有無を、把握することです。
会食と言っても、毎年する訳ではありませんし、駅から近ければ、駐車場は狭くても大丈夫です。
全てが揃わなくても、自分の求める条件をクリアしているかが、肝要です。
セールストークを鵜呑みにせず、必要な施設を必要な料金で・・が「設備」のポイントです。
お墓の広さと言っても、個々のイメージで、かなりの差があります。
田舎の、6畳位のお墓を見て育った人には、3㎡でも小さく感じます。
逆に、都内の寺院墓地を墓参して来た人では、1.5㎡が広く感じます。
どれだけの面積があれば充分かと言えば、現在求められるお墓ならどれでも大丈夫です。
但し、墓誌や灯篭・地蔵尊などの、付属品を希望しないことが前提条件です。
付属品を設置するなら、それなりの大きさが必要になります。
付属品を除き、最低限必要なものは、納骨室・石碑・花立・香炉です。
あとは宗派により、塔婆立位です。
それ以外は、全てオプションになります。
関東近郊だと、千葉県以外では最低面積の制限がありません。
従って、売り出し価格を安く設定したい為、出来るだけ区画を小さくする業者がいます。
寺院墓地でも、沢山の檀家さんを収容したいので、同様に小さい区画を設けます。
注意したいのは、骨壷が1~2個しか収納出来ない場合があることです。
そういった墓所では、2体目から「納骨袋」で納骨しなければなりません。
予め理解した上で、お求めになるなら構いませんが、業者によっては説明をしないことがあります。
後日のトラブルを防ぐためには、最低限の知識が必要です。
目安としては、墓誌は3㎡以上、灯篭・地蔵尊は4㎡以上が必要ですが、間口×奥行きの寸法にも左右されます。
あくまでも、現地での確認が必須でしょう。
また、求める面積に見合った石碑の大きさがあるので、広ければ広いだけ費用は嵩みます。
隣より小さくても構わないなら、別の話ですが・・
現在の様に「○○家」として求めるお墓は、買い替え・建て替えが無いつもりで、ご予算とご希望に合った広さを
ご検討されることが、肝要でしょう。
見栄を張るつもりはないけど、せめて両隣と同じ程度で・・と考える方が多いようです。
業者のアドバイスを受ける前に、自分なりのシュミレーションをきちんとされることを、お勧めします。
お墓に掛る「価格」は、前項の「距離」や、次回以降に述べる「面積」や「設備」などと、
密接に絡んで来ます。
お墓の「価格」には、大別して「場所」に掛る部分と「工事」に掛る部分に分かれます。
同じ工事内容で、同じ大きさなら、大きな差にはなりません。
場所に掛るものは、「墓地代」と毎年必要な「管理料」に分かれます。
寺院墓地などでは、他に「護持会費」や「付届け」などの、費用が掛る場合がありますので、
事前の確認が必要です。
ここで注意したいのは、「墓地代」は求める時点のみ必要な費用ですが、所有権は付かない点です。
不要になった際は、「無償返還」になります。
また、同じ墓域内で、同じ面積でも、向きや場所によって、価格差がある場合があります。
すぐ近くの別の墓地での、価格差があるケースもあります。
比較の際は、1㎡当たりいくらなのかを、計算すると比較し易いでしょう。
一般的には、角地や南向きなどの、人気のある場所を割高にしているようです。
いくらだと「高い」かは、生活レベルによって異なりますが、数か所の候補を比較すれば、
その近辺での「相場」が判るかと思います。
墓地代は、近隣の坪単価より高いのが普通です。
これは、「駐車場」や「管理事務所」「休憩所」或いは「通路」などの共有部分の費用が上乗せされるからです。
1回限りの「墓地代」の比較だけでなく、前述した「管理料」や「護持会費」などのランニングコストを含めた
「費用」の考慮も大切な要素です。
また、「名義変更」や「埋蔵料」など毎年でなくとも、必要な費用は確認しておきたいものです。
千葉県のある霊園では、名義変更費用が、50,000円という所もあります。
近隣では、5,000円~10,000円が相場です。
「所有権」がつかず、転売出来ない「お墓」だけに、事前の確認は、最低限行いましょう。
どこの墓地でも、一度納付した「墓地代」や「管理料」などは、返却されないことが多いからです。
不動産物件と違い、お墓の為に転居することは、殆どありません。
そこで、自宅からの「距離」が比較的重視される傾向にあります。
一番いいのは、歩いて行けることでしょう。
次は、自転車で、或いは駅前、またバス停が近い、車で5分等々・・
問題は、どこに住んでいるかで、上記の難易度が違ってきます。
都心部にお住まいであれば、かなり困難です。
また、都心から60km離れていれば、簡単にクリア・・です。
ここで考えて頂きたいのは、墓参の頻度です。
毎日通勤するのであれば、「歩いて」や「バス停近い」は、重要でしょうが、年に数回ならどこまで
拘るべきかは、意見の分かれるところです。
勿論、「毎週墓参したい」方は、別の話ですが・・
不動産と同じで、都心に近ければ近いほど、費用は嵩みます。
「費用」については、次回の「価格」で述べますので、今回は「距離」に絞ります。
交通手段での注意事項は、バス停などは、採算によっては廃止の可能性の考慮が必要。
これは過疎化が進む電車路線でも、同様です。
また、車の手段も、運転しなくなったとか、車を手放す可能性を考える必要があります。
お墓までの距離は、10年・20年先のことまで考えることが、肝要と言えます。
墓地を求めるにあたって、自分なりの優先順位を決めないと、焦点が絞れませんが、「距離」を
何番目に重視するか・・じっくりご検討ください。
地方自治体が管理・運営する墓地を総称して、「公営霊園」と呼びます。
公営霊園の中で最も歴史が古く(明治7年開設)、使用者数が多い代表的なものが、「都立霊園」です。
現在募集しているのが、多磨・小平・八王子・八柱・青山・谷中の六ヶ所です。
以前は、都立霊園は使用料(墓地代)が安く(どこでも一律料金)、庶民の味方・・でした。
しかし、近年は「受益者負担」との考え方から、霊園毎に使用料を設定し直した為、使用料だけを見ると、
民営霊園の方が安価な場合があります。
都立霊園の中で一番安い八柱霊園は、1㎡当たり 195,000円ですが、小平霊園は808,000円、
多磨霊園は903,000円、青山に至っては2,956,000円と、かなり高価です。(全て1㎡当たりの価格)
また、年一回の抽選倍率は、平均10倍前後と高い倍率になっています。
こういった背景から、民営霊園が昭和40年代から首都圏近郊に造られ始めたようです。
墓地に関する情報を得やすくなった昨今と違い、規制する条例は自治体ごとに異なり、基となる法律は
土葬が多かった昭和23年施行の「墓地埋葬に関する法律」とトラブルの温床は沢山あります。
また、最近は墓地経営は宗教法人でないと、墓地の申請が出来ないことも、トラブルを引き起こす要因です。
この点の諸問題は、別の機会に述べます。
この項でのポイントは、公営霊園・民営霊園の「使用規則」などは、都立霊園を基準に作られていることが多く、
その都立霊園は、以前のように必ずしも安さや利便性からみて、「満点」ではないということです。
勿論、宗教的制約がないとか、管理料が安いなどのメリットはあります。
抽選で当たれば・・が大前提ですが。
公営霊園は、自治体によって無い地域があるのも、民営霊園が増えた理由です。
居住地区に公営霊園があるのか、予定はどうか、募集条件は?など、お墓を探す第一歩です。
業者に相談する前に、最低限調べてみましょう。
お墓を選ぶ要素の中で、上位に挙げられるのが「家から近い」です。
しかし、自分の家の隣にお墓が出来てもよい・・と言う人は皆無です。
線香の煙や匂いがしたり、彼岸や盆などに車の渋滞・・いいことは殆どありません。
県や市が運営する「公営霊園」も全ての地方自治体に存在する訳では、ありません。
地方自治体側からみても、税金が取れず、住民の反対があり、議員の票に結びつかない・・
どこでも積極的な設置を、しないでしょう。
公営霊園で、賄えない部分を民間のいわゆる「公園墓地」や昔からある「寺院墓地」がカバーします。
これとても、近隣の理解が得られないと、開園出来ません。
過疎地なら、反対運動も起きませんが、開園しても販売が伴わない・・
市町村単位での「条例」で墓地の新規建設を、制限している場合もあり、需要を満たすには、
さまざまな問題をクリアしていかなければなりません。
必要としている人にとって、近さは重要ですが、思い通りの物件を求められるかは、居住地により差があるのが、
現状です。
昭和62~63年頃、都心部の寺院墓地で、既存墓地を区画整理して、マンション形式のお墓が
売り出されたことがあります。
屋内墓地で、雨に濡れずにお墓参りが出来るのを、メリットとして掲げてました。
また、墓石が汚れず、傷まないのも長所として・・
狭い敷地を有効利用する、一つの戦略でしたが、あまり普及しなかったようです。
消防法の点から、「線香をあげられない」や排水の面で「墓石に水をかけられない」デメリットが
受け入れられなかったようです。
雨や雪、風に晒されても、四季折々を感じながらの墓参が、日本人に好まれているのかも知れません。
お墓に何を求めるかは、十人十色ですが、自分に合ったスタイルや、自分のニーズを認識した上での
お墓選びが、遠回りでも近道と言えるかも・・
とは言え、一生に一度あるかないかのことですから、専門家のアドバイスを聴いて、悔いのないお墓選びが
肝要かと思います。
皆様のお墓選びのヒントになれば、幸いです。
以前先輩に、
「墓とは、漢字の組み合わせで分かる様に、草が生えて、日が当たり、
人が大の字になれて、土がある」と教わったことがあります。
しかし、最近のお墓は、価格競争が激化し、どんどん小さくしていった結果、漢字本来の内容を、
網羅していません。
千葉県を除く、首都圏では最低面積の規定がない為、0.42㎡や0.48㎡など、掛け算九九が
上達しそうな区画が、多数見受けられます。
小さな面積の区画に、色々な付属品(墓誌や灯篭など)を設置しようとすると、何がメインなのか、
ある意味見苦しさを、感じます。
その区画に見合った付属品の設置を勧めるのも、石材店の良心かも知れません。
また、大きさによっての守備範囲も、あるかと思います。
例えば、墓誌を別立てで入れるなら、3㎡以上とか、灯篭なら4㎡以上などです。
経済状況の悪化により、年々求める墓地の大きさが、小さくなっていくので、
「人が大の字になれる広さ」の墓地は、絵に描いた餅かも・・・